元旦
元旦は朝から家族全員が揃い、おせち料理とお雑煮を食べるのが習わしです。結婚前も結婚後も自宅で正月を迎え、相変わりなく元旦を迎えています。以前は新年の挨拶で訪問客が何組かありましたが、ここ数年は殆ど無くなり、最近は近くの神社へ初詣に家族揃って行くのが恒例です。
ただ、新年早々大変混み合うこともあって、このところ元旦にひとり早起きして、家族とは先に初詣に出掛けるのが習慣化しています。その際、一年の道行を決めるような気がして引く初おみくじが楽しみです。
初おみくじは大吉が3割といわれますが、出た年は占い通りの幸があったと思えるから不思議です。正月早々、凶を引かないようにと祈る気持ちになります。若い頃は何とも思わなかったのですが、占いにはまる人が多いのが少しは理解できるようになってきたのは人生の経験が深まってきた証拠でしょうか。
話は変わりますが、このところ日本酒の美味しさに目覚めました。出版業界の担当をした頃に経営者達に会食で日本酒を勧められたのがきっかけです。お酒に合う肴、特に好物なのがいくらや筋子といった魚卵を中心につまみながら、朝から誰にも遠慮無く一日中飲んでしまうのが元旦の醍醐味です。
肉食志向で魚離れが加速している日本ですが、和食に魚介類は切っても切れない関係です。もちろん、日本酒を嗜むためにも。

サケ(鮭)
2024年の秋はサケが凶漁でした。国内漁獲量の9割を占める北海道で激減したのです。卸値は2023年比3倍近くと過去最高値になりました。同様にサケの卵であるいくらも最高価となり、おせち料理への影響も避けられませんでした。
サケ漁は9~10月がピークで特に網走を含む最大産地のオホーツク沿岸は漁獲量が8割から9割の激減となりました。こんな不漁は経験が無いと漁師達も嘆いていたようですし、正月の新巻鮭が作れないと水産加工会社も悲鳴を上げました。
いくらはさらに高級品となり、北海道産の新物の卸値は2023年の2倍となりました。日本のいくらの消費量の8割は北米産の輸入卵が占めていますが、やはり2023年に比べてこちらも高くなっています。国際的に品薄らしいのと円安や世界的な回転ずしブームでいくらが争奪戦になっています。
海や川でとれるサケは大部分が人の手で孵化して放流した魚であり、秋に川を遡上した親魚から採卵し、受精して稚魚まで育てます。春に稚魚を放流すると海で3∼4年かけて成長し、産卵のために故郷の川へ帰ってきます。これこそが自然の再生力を最大限活用した日本の伝統的な「育てる漁業」の典型です。
しかし、海の環境変化でサケの回帰率は1∼2%と低迷しています。毎年、漁業関係者達が費用負担し、相当量の稚魚を放流していますが、長引く不漁で漁業経営が悪化して孵化事業の維持が困難となる地域も出てきています。また、高水温に加えてサケの卵の一大供給地である網走川の近隣の湖で青潮と呼ばれる水中酸素が欠乏する現象が発生し、その影響で網走川の親サケが大量死するなど春の放流への支障が不安視されます。
育てる漁業と放流
育てる漁業の代表格として、放流には半世紀以上の歴史があります。放流は限りある自然の恵みを増やすべく、自然に数が減りやすい卵や稚魚を人の手で守れば、いずれは大きく成長して自然の幸をもたらすとの考えに則っています。
1960年代に国が瀬戸内海で放流事業を開始、全国へ展開しました。海外の漁場の縮小や環境の悪化など魚介類の減少が避けられず、放流事業の推進により漁獲量を確保するために行われました。中国や韓国、アメリカやロシアでも放流は盛んですが、特に日本は放流大国として知られています。国が2022年に策定した栽培漁業基本方針でも推進が後押しされ、自治体がどの種類をどれだけ放流するかなどの計画が示されました。
トラフグや絶滅が心配されるマツカワなど放流による資源量増加の成功例もありますが、放流魚の回収率は平均すると数%程度で、自然変動に埋もれてしまう位の効果しかないとされ、真鯛やヒラメの放流や稚魚の生産を中止する自治体も出てきました。
他の魚がいる河川に別の魚を毎年放流すると生息場所や魚の性質といった条件を変えても在来の魚を追い出してしまう状況が研究されています。放流で一時的に数が増えた魚は河川を独占して他の魚は餌にありつけず、すみかを追われてしまうのです。
過剰に放流されると同種でも争いが起こり、餌やすみかを争った結果、河川に住んでいた魚も含めて共倒れしてしまいます。
また、放流する稚魚は少ない親魚から卵をとるため、同じ遺伝子が増えると多様性を失って環境の変化で滅びる可能性も指摘されています。水槽で育てた後に放流する魚は弱くなりがちとの傾向も見受けられます。
放流が真に必要な条件としては希少な種類を保全する場合などが挙げられます。
育てる漁業を進めるには産卵する場所の整備や遡上しやすくするための魚道を作ったりする地道な活動が大切です。漁では漁業資源量と回復量の管理が求められ、捕る量の調整が肝要です。

淡水生物の危機
英国の科学誌ネイチャーに国際自然保護連合の調査・研究が発表され、世界の川や湖などの淡水に生息する魚やトンボなどの昆虫類、ザリガニなど2万3496種の内、4分の1が絶滅の危機に瀕しているとしています。
地球規模での絶滅リスクが高まっていて、当然、日本も深刻な事態であり、国内固有の淡水魚100種の内、約40%が絶滅危惧種とされています。
主な要因としては、河川の改修による環境悪化、水田の減少と水田周辺の生息地の減少、外来種の存在と増加傾向、などが挙げられます。危機の深刻さを理解して外来種の拡散防止などへの取り組みが急務です。最大の要因は地球温暖化であるのは間違いありません。
世界気象機関(WMO)によると2023年は河川の流量が過去30年間で最低水準となり、最も川が乾燥した年としています。
氷河の融解も過去50年間で最大であり、2023年に記録した氷河の消失は6000億トンの水量に達し、国土交通省の調べでは日本の年間降水量約6600億トンに迫る規模なのです。
この影響により世界各地で水害が頻発しています。水が多過ぎても少な過ぎても生活や生態系に代償を伴います。
地球温暖化の速度を和らげる取り組みが生物との共存を図り、生態系を守るための絶必条件なのです。










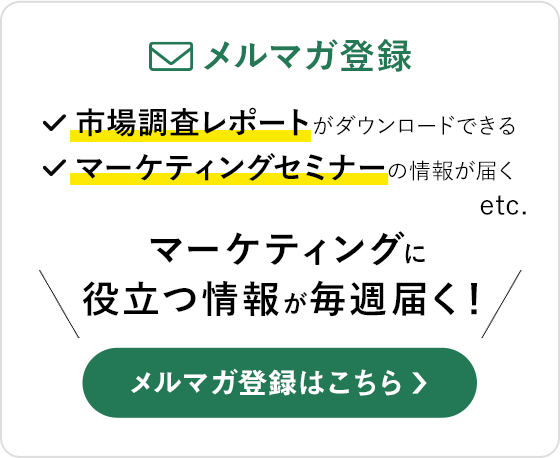







株式会社創造開発研究所所長、一般社団法人マーケティング共創協会理事・研究フェロー。広告・マーケティング業界に約40年従事。
日本創造学会評議員、国土交通省委員、東京富士大学経営研究所特別研究員、公益社団法人日本マーケティング協会月刊誌「ホライズン」編集委員、常任執筆者、ニューフィフティ研究会コーディネーター、CSRマーケティング会議企画委員会委員、一般社団法人日本新聞協会委員などを歴任。日本創造学会2004年第26回研究大会論文賞受賞。