スピーカー紹介

株式会社ポーラ 顧客戦略部 部長
公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 理事
公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 デジタルマーケティング研究機構 代表幹事
中村 俊之 氏

株式会社クー・マーケティング・カンパニー
代表取締役
音部 大輔 氏
ID共通化によるチャネルシームレス化で、顧客一人ひとりに向き合う
株式会社POLA 中村 俊之氏(以下中村):まず、POLAが設計する顧客体験についてご説明します。POLAには、化粧品を販売する百貨店カウンター、オンラインストアに加えて、化粧品とエステサービスをご提供するポーラのお店、施設向けのアメニティ販売を取り扱うBtoB事業といった4つの事業を有しています。

POLAではチャネルシームレスに、より良い顧客体験を提供するため、2023年4月より、会員IDの共通化を行いました。各チャネル独自で運営されていた会員サービスやコーポレートサイト・ECサイト、アプリを統合することで、どのチャネルで買ってもPOLAのサービスを共通してお届けするということを目指しています。

株式会社クー・マーケティング・カンパニー 音部 大輔氏(以下音部):なるほど。お客様がどこで何を買われたのかもわかるようになった、ということでしょうか。
中村:おっしゃる通りです。
実は「共通化」という言葉にもこだわりがあります。「ID統合」「顧客統合」という言葉も良く使われますが、IDも顧客も元々は1つであって、統合されるべきはブランド側の販売の仕組みだと考えています。ですので、あえて「共通化」という言葉を使っています。
IDの共通化やデータの利用は、DX文脈で社会全体においてトレンド的に取り組まれています。POLAはオフラインでの販売が強みにはなりますが、共通化を行った理由は、POLA独自の体験を提供したい、お客様とのダイレクトな接点を大事にしたいと考えているからです。
デジタルが当たり前になった世界でどのようにして一人ひとりにPOLAらしいおもてなし、豊かな時間をお届けできるかという考えが、ID共通化をはじめとした最近の取り組みの背景にあります。
音部:POLAに、一人ひとりに向き合うという文化があるがゆえのID共通化。データを取りたいというよりは、消費者をよりよく理解したいという捉え方がなされているのですね。
組織横断型のプロジェクトを進めるためのステップ
中村:ID共通化を進める上で難しかったのが、組織を横断してプロジェクトを進めることです。社内には様々な役割を持ったステークホルダーが存在します。施策を進める上で、この枠組みをまたいで、共通の目的に向かっていくことが求められました。
組織横断プロジェクトを実行・成功させるためには大きく2つのステップがあると考えています。以下の図はそのステップの例です。

Step1では関係組織間が腹落ちする“あるべき姿”を描きます。あるべき姿とは、会社のビジョン・ミッション(POLAの場合、「私たちは、美と健康を願う人々及び社会の永続的幸福を実現します」)を踏まえた上で、時代や会社の状況と照らし合わせて何ができるか、という伸びしろを描いていくものです。施策の規模が大きい今回のケースですと、関係者が多いこともあり、数か月かけてこの骨子を作り、そこから改善を重ねていきました。
音部:中村さんは、ビジョン・ミッションを前提にして、組織横断のプロジェクトを実行したいと思ったとき、Step1では具体的にどのような行動をとられますか?
中村:1.伸びしろの共同整理 2.ターゲットの設定 3.ゴールの定義を、それぞれ分けてやるのではなく、同時に並行して行います。ワークショップを開催したり、社内のありとあらゆる部門に出向き話を聞くことで、伸びしろを探っていきます。直接話し合うことで、ステークホルダーに「自分たちもこのプロジェクトに関わっているのだ」という意識を持ってもらうことも、組織横断のプロジェクトの序盤には欠かせませんね。
Step2では、Step1で描いた理想を実現するための手段を立案し、実行します。
音部:デジタルが浸透した世界で、事業チャネルをまたいで御社らしい「豊かな生活の創出」というビジョンを共有し実行するのがStep2ですね。Step2の注意点を教えてください。
中村:「終わりを作らない」ということかなと思います。一度決めたものが最後までそのまま進み続けるということは非常に難しいものです。プロジェクト憲章や終結プロセスは、プロジェクト単位で最初に作るものではありますが、組織横断プロジェクトのように複数のものが動いているときは、プロジェクト間でやり取りをしながらその都度、柔軟に変化させる必要があります。そのため、柔軟性と、短いサイクルの中でスコープ定義やKPI設定を見返しPDCAを回すようにすること、この2点が重要であると考えます。
音部:柔軟に対応しつつ、Step2はあくまでStep1で定めた“あるべき姿”を実現するための手段なので、Step1で決めたことを見失わないようにすることが重要ですね。こうすることで、ブランドの本来の目的からかけ離れてしまうことも防げるでしょう。
ブランド定義のフォーマットを解説。消費者を主語とした「ベネフィット」が重要
音部:以下のシートは、組織全体のあるべき姿を描く際にも使える、ブランドを定義するためのフォーマットです。8個の箱があり、上の箱ほど重要で、下の箱は上が決まると自ずと定まってくることが多いです。

中村:ブランド定義のエッセンスが詰まっている印象です。「大義」から始まっているのも、我々が進めてきた方針に近いものを感じます。こちらを記入していく上でのポイントやコツはありますか?
音部:そもそも何のためにこのビジネス、ブランドがあるのか、一番上の箱でしっかり定義することが大事です。ブランドとして実現したいことを考えた上で、誰にどのような「ベネフィット」を提供するかが重要です。ベネフィットは「機能」と混乱しがちですが、機能はブランドを主語にしたものです。一方でベネフィットを考える上では、主語は消費者です。提供する製品・サービスを通して、消費者がどのような「良いこと」を得られるのかを明確に表しましょう。
例えば、紙おむつを販売する会社であれば、「もれない・蒸れない」がベネフィットであると思われがちですが、これは機能であり、その先に「ぐっすり眠れる」といったベネフィットが考えられます。これがいずれブランドに固有の意味になっていくので重要です。ターゲット消費者とベネフィットを明確にし、ブランドらしい記述ができるようになると、先ほどのStep1の腹落ちフェーズのように、このブランドがどうなりたいかを他部門と共有するときに、全員が同じ方向に向かってプロジェクトを整備していきやすいと思います。
つい目先のできることや業務に目が行きがちですが、常に消費者の目線を中心に置いておくことでそれが共通言語となり、合意が取りやすいのではないでしょうか。
組織横断でアイデアを引き出し、施策の適切なタイミングがわかる「パーセプションフロー・モデル」
音部:販売チャネルを含む様々なタッチポイントを楽器に例えると、ひとつの楽譜があることで、オーケストラの演奏がうまく行きます。ここで、全体のオーケストレーションの設計にも役立つ「パーセプションフロー・モデル」を紹介したいと思います。

中村:このフォーマットを使用することで、ステークホルダーのクリエイティビティを更に引き出していけそうですね。
音部:元々このモデルはマーケティング活動全体の設計図です。実際にパーセプションフロー・モデルを作りながら、「消費者は、実はこういうことを感じているのではないか」などと皆で考えていくケースもあります。データによってできることが増えたからこそ、データの解釈などを話しつつ、作りながら考えていくことが役に立つこともあります。「ホモ・ファーベル」という表現があります。手を使い、物を作りながら考えるヒトという意味です。頭だけで完結できる設計もありますが、手を使うことでイメージしやすくなる、といったことも少なくありません。
中村:今回の、組織横断プロジェクトを実行する上で、ステークホルダーと協働しながらプロジェクトを描いていくフェーズはとても多かったです。複数の人が関わって手を動かしながら物事を考えることは、事業に広がりをもたらしてくれると思います。プロジェクトマネジメントの際に、一つのプロジェクトとして目指すべきものを作っていける地図になりそうです。
音部:会社としてできることが増えた際に、「何をいつするか」の示唆はこちらのモデルから得られそうですか?
中村:そうですね。お客様を想像しながら、自分たちのアイデアを提供できるタイミングを俯瞰して整理していく際に、とても有用だなと思いました。
どれほど良いアイデアという種を思いついても、植える場所を間違えてしまうと、その結果、花を咲かせることができないということは、課題としてよく見られます。一方で、パーセプションフローのような地図があることで、それぞれの土壌が分かっていると、「このアイデアはここ」という風に、それを実行するタイミングを見極めることができるのではないでしょうか。
音部:では、まとめに入っていければと思います。
データというと、とても数値的で冷たいイメージになりがちですが、データは消費者を描写したものでもあります。「データ中心」は「消費者中心」と言い換えても良いかもしれません。今回の対談では、消費者を中心に据えたマーケティング組織を構築するにあたって、どういうことに気を付ければ良いのかを整理できたと思っています。関係各所の皆が参加して、腹落ち感のある“あるべき姿”を一貫して持っておくこと、加えて、メンバーのクリエイティビティを促すような仕組みを作っていくことが重要なのではないでしょうか。










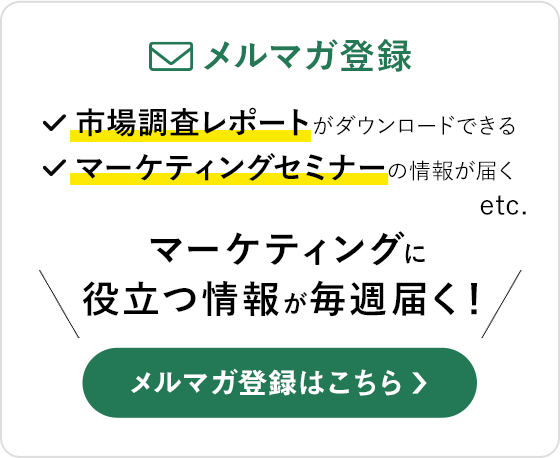






2025年入社予定の大学4年生です。